ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
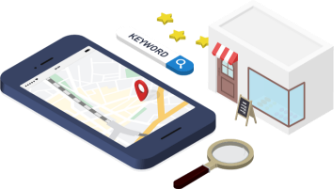
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
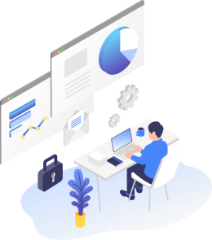
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
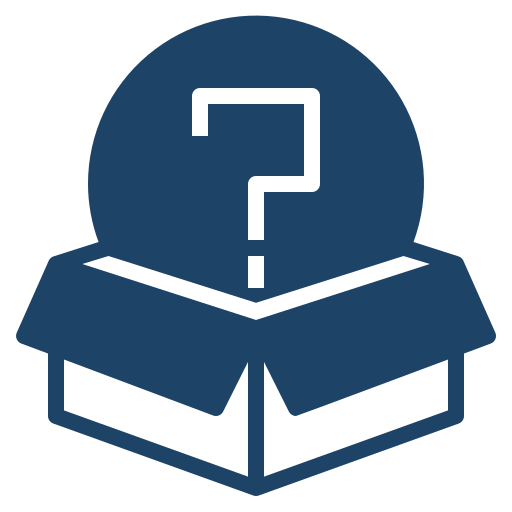
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見るネガティブなサジェストの削除|サジェスト対策で風評被害をなくす
Google・Yahoo!の検索欄に単語を入力すると、複数のキーワード候補が表示されるのを見たことはありませんか?
このキーワードのことをサジェストキーワードといいます。サジェストとは予測変換を意味していて、ユーザーが検索しているキーワードを予想して提案する機能です。
便利な機能ですが、サジェストにネガティブなキーワードが表示されることがあります。ネガティブなキーワードの表示は、個人・企業において風評被害の原因となるので、対策をおこない削除することが必要です。
そこで今回は、サジェスト対策について解説していきます。
サジェスト対策とは
サジェスト対策とは、特定のキーワードをサジェストに表示、または非表示(削除)する対策のことです。
サジェスト対策は、主に2つの目的で行われます。
- 特定のキーワードを表示させWebサイトのアクセスアップ
- 風評被害対策のため、ネガティブなサジェストを削除
この記事では、風評被害のサジェスト対策に焦点をおいて書いていきます。
なぜなら、サジェストはGoogleやYahoo!といった検索エンジンに表示されるため、ネガティブなキーワードがあれば経営に影響を及ぼすからです。
なぜサジェスト対策が必要なのか
GoogleやYahoo!で企業や人、商品などを検索する際、「ブラック」「パワハラ」「詐欺」「悪質」といったネガティブなサジェストが表示されることがあります。
このようなキーワードが表示される状態をサジェスト汚染と呼びます。
サジェストが汚染される原因は、次の2つです。
- ネガティブワードの組み合わせで一定数検索されている
- ネガティブワードを含むサイトやコンテンツがある
一度ネガティブワードが出ると、興味本位で検索する一般ユーザーが増えます。すると、サジェストに定着してしまいます。
サジェストに表示されるキーワードは多くのユーザーが目にし、クリック率も高いです。あるマーケティング会社の調査では、70%のユーザーがサジェストを利用したことがあるとしています。
ポジティブなキーワードであればイメージアップになますが、ネガティブなキーワードの場合、事実無根であっても、イメージダウンになるのは避けられません。
一度でもマイナスイメージがつき、信用や売上がダウンしてしまうと、回復は困難です。特に、デマや誹謗中傷でサジェスト汚染されている場合は、早急な対策が必要です。
サジェスト対策、ネガティブキーワードを削除する方法
ネガティブキーワードは、早めの削除が重要です。サジェスト対策の方法を紹介します。
Googleサジェスト削除申請フォームから依頼
Googleサジェストは、自分で削除依頼ができます。Googleのオートコンプリートポリシーに違反し、権利侵害が発生していると判断されるとサジェストが削除されます。
申請は、Googleサジェスト削除申請フォームからおこないます。
削除申請は1回目に通らないと2回目も通らない可能性が高いので、1回目にしっかり詳細を書き申請するのが重要です。
ネットに強い弁護士に依頼
サジェストの削除申請は、法的根拠が必要です。個人ではどのような権利に侵害されているのか、法的根拠を示すことが難しいため弁護士に依頼することをおすすめします。
インターネットに強い弁護士に依頼する方法することで、被害内容や中傷事実の有無を調べ、法的にサジェストを削除できる可能性が高くなります。
依頼するときは、依頼した弁護士が代理削除申請をしてくれるか、弁護士への依頼時に仲介業を介さないことになっているか、確認してください。
ただ、弁護士への依頼は金額が高額になりやすいです。相談のみで料金がかかる、結果がでなくても着手金はかかるなどの場合、痛手となります。
風評被害対策を専門とする会社に依頼
風評被害や誹謗中傷対策専門会社への依頼では、高確率かつ最短数週間で非表示にできます。
サービスを選ぶポイントには、サジェスト汚染の原因分析ができる、再発防止補償などのサポートがある、対応が速いなどがあります。成果報酬型では、成功しなければ費用はかかりません。
ネット掲示板などへの誹謗中傷や、名誉毀損の書き込みについても相談できます。相談や見積もりは無料の場合が多いため、ぜひ問い合わせてみてください。
サジェスト対策の注意点
サジェスト対策には、いくつか注意点があります。
対策を止めると再表示する可能性がある
サジェスト機能はGoogleやYahoo!が管理しているため、検索エンジン側のシステム変更があると、非表示化できたキーワードが再表示することがあります。
対策を止めると表示されたままになってしまうため、続けての対策が重要です。
風評を完全になくすことはできない
サジェスト対策はネガティブワードを非表示にするものなので、風評自体を完全になくすことはできません。
風評被害を根本的に解決するには、経営体制などの見直しも重要です。うまくいけば、時間をかけて自然とネガティブワードも消える可能性があります。
まとめ
人の行動は、イメージに大きく左右されます。企業や商品のブランドイメージが下がると、倒産など存続に関わる事態になる恐れもあります。
一度下がったイメージを上げるのはかなりの時間と労力がかかるため、サジェスト汚染がわかったら、早急に対策すること大事です。
ホストラブ(ホスラブ)削除依頼の手順|注意点や消えないときの対処法
ホストラブ(ホスラブ)は月間200万人ものユーザーが利用している、夜の業界の情報交換に使われている大規模な掲示板サイトです。
これだけ利用者が多く、また夜の業界に関する情報交換サイトということもあり、個人名や店名などを挙げた誹謗中傷などの投稿がされることも少なくありません。
ホストラブで誹謗中傷などの投稿がされた場合、削除依頼をおこなうにはどうすればよいか、またその注意点などを詳しく解説していきます。
ホストラブの削除基準
まずホストラブの「削除ガイドライン」によれば、投稿された内容のうち以下のような基準で削除するかどうかの判断をおこなっています。
個人名・住所・所属について
- 情報価値がある、公益性があるものは削除されません。
- 公開されたサイト、全国的マスメディア、電話帳で確認できる、などの情報は削除されません。
- 趣旨説明や公益性がなく、誹謗中傷が目的などの場合は削除対象です。
電話番号について
- 一部伏せ字、それを示唆するような文字列なども原則としてすべて削除対象です。
- 投稿者の自己責任であるものは削除されない場合があります(本人が公開したと判断できるもの、リンク先で確認できるものなど)。
メールアドレス・ホスト情報について
騙りや悪意が明らかで攻撃を目的とするもの、晒し目的などの場合は削除対象です。
誹謗中傷について
- 公益性があり掲示板の趣旨に則した内容、直接の関係者に関する記述は削除しません。
- 個人(ホストを含めた有名人を除く)を特定する情報を含んだ投稿はすべて削除対象です。
私生活情報について
公益性のないプライベートな情報は、個人(ホストを含めた有名人)が完全に特定されなくても、中傷していなくても、すべて削除対象です。
ホストラブに削除依頼する際の注意点
ホストラブの運営側に削除依頼をする場合、次のような点に注意が必要です。
自分で削除依頼した場合は履歴に公開される
削除依頼をおこなう際になぜ削除を希望するのか、その理由や根拠を記述することになりますが、この内容は「削除依頼履歴」のページで公開されてしまいます。
そのため、依頼時にあまりプライベートな内容や詳細を書きすぎると、二次被害につながってしまうので、気をつけてください。
依頼文はガイドラインを参考に「個人情報のため」や「誹謗中傷にあたるため」など、簡潔に理由を述べる程度にしておくとよいでしょう。
スレッド単位の削除は難しい
削除依頼は、基本的にガイドライン違反のあった投稿を対象としており、スレッド(掲示板ごと)単位での削除はむずかしいです。
スレッドごと削除されるには、その投稿すべてがガイドラインに違反している場合のみになります。この判断は、削除をおこなう「削除人」次第です。
削除業者の利用は違法
削除依頼を弁護士に代行してもらうことができますが、弁護士以外の業者に依頼すると、「非弁行為」として弁護士法という法律に違反してしまいます。その場合、引き受けた業者だけでなく依頼者も罰せられるおそれがあります。
ホストラブの削除依頼ガイドにもこれに関する記載があり、違法な削除代行をおこなう業者は事業者名・サービス名などを公開するとしています。
ホストラブの削除代行をおこなえるのは弁護士だけなので、このような業者に依頼しないよう注意してください。
ホストラブに書き込み削除を依頼する手順
では、どのように削除依頼をおこなうのか、その手順や各項目の入力方法について解説していきます。まず、「削除依頼フォーム」にアクセスしてください。トップページ下部にもリンクがあります。
フォームにはつぎのような入力項目があります。
- スレッド番号
- レス番号
- 削除理由
- お名前
- メールアドレス
なかでも重要となる1~3の入力方法について見ていきましょう。
1. スレッド番号
スレッド番号は、スレッドページのURLで確認できます。たとえばURLが「http://kanto.hostlove.com/**/(14桁の数字)/1」の場合、この14桁の数字がスレッド番号です。
2. レス番号
レス番号とは、書き込みのすぐ上に表示されている数字のことをいいます。削除してほしい投稿が複数ある場合、カンマ(,)で区切って入力します。
3. 削除理由
この部分はホストラブの「削除ガイドライン」を参考にして、削除してほしい投稿内容がどのようにガイドラインに違反しているかを500文字以内で説明します。
前述のとおり依頼文は公開されるため、詳細を書きすぎないように注意して、削除を依頼する理由を記述してください。
要確認!削除依頼の成功率を高めるために
削除依頼をすれば、かならず該当の投稿が削除されるとは限りません。ガイドラインに違反していなければそのままになります。すべては削除をおこなう「削除人」の判断次第です。
では、どうすれば削除してもらいやすいのか、その成功率を高めるコツをご紹介します。
利用規約
ホストラブには、ガイドラインのほか「利用規約」もあります。利用規約には「禁止行為」の記載があり、投稿に関しては以下のように定められています。
2:虚偽または故意に誤解を与える発言
3:民族的・人種的差別につながる発言、倫理的観点から問題のある発言
6:本サイトの目的及び開設されたテーマとは無関係な発言
7:本サイトが禁止を明示した発言または削除した発言と同一または類似する内容の発言
10:第三者の個人情報を無断で収集、開示する行為
11:第三者に対する誹謗中傷または名誉き損、もしくは他者に対して不利益または不快感を与えるおそれのある発言
13:公序良俗に反する行為
これをもとに「利用規約の~に違反する」と記載すれば、主張の正当性が高くなります。
削除依頼履歴
ホストラブの「削除依頼履歴」ページでは、過去に受理された削除依頼の内容が公開されています。この履歴から、実際どのように依頼の申請がおこなわれたのかを確認できます。
掲載されているのは削除に応じてもらえたケースなので、これを参考に依頼文を考えると成功率を高めることができるでしょう。
削除依頼がホストラブに受理されなかったときの対処法
削除依頼ガイドによれば、削除は96時間を目処に実行されます。これを大きく過ぎた場合、依頼が受理されなかったといえるでしょう。
受理されなかった場合でも、どうしても削除してほしい投稿があるかもしれません。その場合の対処法について解説します。
依頼内容を見直し再度申請する
削除依頼が受理されなかった場合、依頼した内容に間違いがないか、問題はなかったかを再確認してみてください。たとえば、以下のような部分です。
- スレッド、レス番号が間違っていないか
- 削除理由がガイドライン違反にあたるか
これを見直したうえで、再度申請をおこなってみてください。また、削除をおこなう削除人はボランティアです。「早くしてほしい」など失礼な発言はしないようにすることも重要です。
弁護士に削除依頼する
自分で削除依頼しても受理されなかった場合、法律のプロフェッショナルである弁護士に代行してもらう方法もあります。
前述のように削除されるかどうかは削除人の判断によるものです。受理されなかった場合でも、投稿内容にまったく違法性がないといえません。
あきらかに名誉毀損やプライバシー侵害などにあたる投稿でも削除されないようであれば、ホストラブの運営会社に対して削除を要求するとよいでしょう。
場合によっては裁判所の仮処分をおこなえば、ほぼ確実に削除できます。弁護士の初回相談は無料という場合も多いので、ためしに話を聞いてみるとよいかもしれません。
ホストラブに誹謗中傷を書き込んだ人物は特定できる?
書き込みした人物を特定するには、弁護士に依頼するしか方法がありません。
手順としては、弁護士を介してホストラブの運営側に投稿者のIPアドレスを開示請求し、そのIPアドレスを提供しているプロバイダーにさらなる情報開示の請求をおこないます。
プロバイダーが情報を開示すれば、投稿した人物の名前や住所、メールアドレスなどを知ることができるでしょう。
ただ、これはネット掲示板などの知識を持った弁護士でなければ難しいため、弁護士選びも重要になります。
まとめ
ホストラブの投稿に関して削除依頼をおこなう手順や、依頼が受理されなかった場合の対処法などをまとめてご紹介しました。
削除依頼が受理されなかった方のなかには、早く消して欲しいからと依頼文が荒いというケースも少なくないようです。
受理されなかった場合でも送信した内容を見直して、再度チャレンジしてもうまくいかなかった場合は弁護士への依頼を検討するのもよいでしょう。
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。


